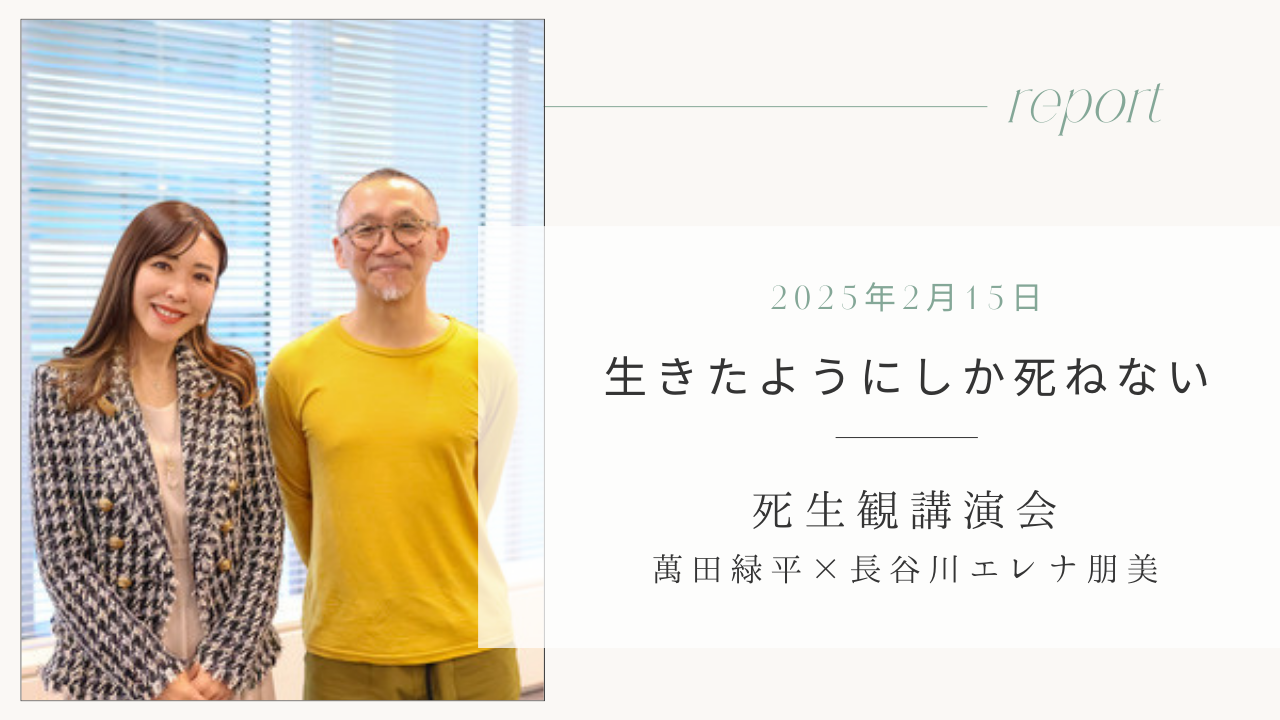2月に開催された「死生観講演会」に行ってきました。
この講演会の登壇者は、在宅緩和ケア医の萬田緑平先生と、経営者で作家の長谷川エレナ朋美さん。
過去にもこのブログでご紹介しました書籍『家で死のう!』の著者である萬田先生と、萬田先生のことを知るきっかけとなったエレナさんの登壇となれば、「もう行くしかない!」と思い、行ってまいりました。
講演会で聞いたお話や、私が感じたことをレポートしたいと思います。
登壇者紹介

はじめに、登壇者のお二人についてご紹介します。
萬田 緑平先生
萬田 緑平先生は、在宅緩和ケア医として、2000人以上の看取りに関わり、「緩和ケア 萬田診療所」の院長をつとめながら、全国で講演活動も行っています。
もともとは外科医として手術や胃ろう造設なども行っていましたが、医療のあり方に疑問を持ち、現在の活動をされるようになったのだそう。
長谷川 エレナ朋美さん
長谷川エレナ朋美さんは、株式会社LUMIERE代表取締役でありながら、15冊の著書がある作家でもあります。
ブログやインスタグラム、オンラインサロンで、心と体の健康や自己との向き合い方、エシカルライフなどを発信されています。
私は以前からエレナさんのブログの読者で、萬田先生の本を知ったのもエレナさんのブログがきっかけでした。
長谷川エレナ朋美さんのお話
まず、エレナさんのお話から始まりました。エレナさんの死生観、看取った祖母のこと、エレナさんが伝え続けているメッセージを改めて聞くことができました。
亡くなった夫のこと
エレナさんは、30歳のときに夫を突然亡くしています。エレナさんにとって彼は、パートナーでもあり、メンターでもありました。
その彼の口ぐせは、
「人生一度きり、
明日死ぬかもしれないし、
やれること沢山しとこーゼ!」
だったのだとか。
まさにその言葉通りに生きた方だったそうです。
彼の死は、エレナさんの死生観に大きく影響を与えたといいます。
看取った祖母のこと
この講演会の10日ほど前、エレナさんは祖母を自宅(祖母の自宅)で看取っています。そのときの経験もシェアしてくださいました。
病院にいるときは、チューブにつながれ、険しい表情をしていた祖母が、家に帰ってきてから、ニコニコと穏やかな表情をしていたそう。そして、エレナさんやご家族に向かって何度も「ありがとう」と言ったそうです。
お話の中で、エレナさんは、おばあさまの実際の様子を写真や動画で見せてくださいました。穏やかな表情をしていましたし、亡くなる前も苦痛を感じている印象はありませんでした。
「ああ、これが穏やかな死というものか」と思いました。
エレナさんが伝え続けているメッセージ「本当に大切なものを大切にする」
これは、エレナさんのブログや書籍でも度々発信されていることでもありますが、エレナさんのお話で改めて心に残ったのは、「命の時間を削るに値することに人生の大事な時間を使えていますか?」という問いです。
「本当に大切なものを大切にする」「本当はどうしたい?」と自分に問いかけてあげること。本質的に大切なことは何か、皆、わかっているつもりでも、日常に追われて忘れてしまいがちです。
それを忘れないようにリマインドする仕組みを作ることも必要、と。そのために、エレナさんは自分と向き合う時間のための手帳をプロデュースしているのだそう。
萬田緑平先生のお話
次は、萬田先生です。萬田先生のお話は、人が「生きている」とはどんな状態であることなのか。根本的なことを考えさせられるお話でした。
人は病気で死ぬのか老化で死ぬのか
萬田先生からは、次のようにおっしゃっていました。
「急に病気になった」と多くの人は言うが「急に」ということはない、みんな階段のようにポンコツ(老化=病気)になっていく。病院で治療を受けても人は死ぬのだ、と。
当たり前の事実のはずなのに、頭のどこか勘違いをしてしまいがちなお話をズバっと突きつけられました。
先生の書籍にも書かれていますが、現在の医療は、少しでも長く生かせること(=心臓が動いている状態)を目指している、と。
だから医療現場では、治らない病気も治療し続けて、本人が苦痛を感じていても、意思表示が出来ない状態になっても、家族の要望で生かされ続ける。つまり延命治療の果てに病院で亡くなる、ということがよく起きているのだそう。
それに、本人が家に帰りたいといっても家族が反対するケースが多いといいます。家族は、家に帰ると死んでしまうと思っているからです。
萬田先生は、家に帰った(=医療をやめた)から死ぬのではなく、寿命(=老化)で人は死ぬのだ、と言います。
萬田先生の緩和ケアとは
萬田先生の緩和ケアとは、患者の心の部分をサポートすること、本人が望むことをサポートすることだといいます。
食べ物や飲み物に制限はありません。飲みたいものを飲ませ、食べたいものを食べさせる。食べられない人には無理やり食べさせない。旅行に行きたいと言われても反対しません。
それは、
・体にいいことしたからって生きられるとも限らない
・誰かにとってはいいことも、誰かにとっては悪いこともある。その逆もしかり
だからです。
そして、家族ができることは本人の希望を「支える」こと。あれはダメ、これはダメと言うことではないんですね。
看取りの事例
萬田先生がサポートした患者さんの動画をいくつも見せていただきました。
高齢の方もいれば、平均寿命よりも随分とお若い方もいました。みなさん、ご本人も家族も穏やかな表情で笑顔も見られました。たくさんの管につながれて苦しそうな姿や悶え苦しむ姿もありません。
自分のお別れ会に参加してから亡くなる人、大好きな旅行にいったあとに亡くなる人、ベッドの上で念願のビールを飲んでから亡くなる人など、みな本人の「希望」を実現できて満足そう。
亡くなる直前にこんなに元気なものなの?と驚いてしまいました。
「体はもうボロボロだけど、心が元気だから元気でいられる」と萬田先生。
萬田先生の書籍にあった「枯れるように死んでいく」とはこういうことなんだな、と感じました。死というのは自然なことなんだ、と思わせてくれました。
「がんばって」よりも「ありがとう」を
萬田先生が繰り返しおっしゃっていたことは、「がんばって」よりも「ありがとう」を。
もう、すでにがんばっているのに、家族は「がんばって」「あきらめないで」の言葉をかけてしまう。これでは患者が辛いだけなのだ、と。
動画の中でも、「ありがとう」を言ってお別れできた人達は、みんな清々しい表情をしていました。
なかには、家族と確執がある関係性や、素直に感情表現をできないタイプの方もいます。萬田先生は、そんな人達が素直に「ありがとう」といえるようなきっかけづくりもサポートしていました。
生きているうちに「ありがとう」「大好きだよ」と言ってお別れすることは、見送った家族の心も救うのですね。
そして、たとえ好きじゃない親だとしても、「産んでくれてありがとう。そのことに感謝しているよ」と言えばいいと萬田先生は言います。この言葉は私にとって救いになりました。
大好きな親を看取り、深く悲しむ知人を見て、私は親を看取るときに同じように全力で悲しむことが出来るのか、自信がなかったのです。
私の気づき
「緩和ケア」というと、なす術がなくなったら行うものというイメージがありましたが、決してそうではなく、終末期の貴重な時間をどう過ごすか、というひとつの選択肢なのだと気づきました。
「枯れるように死んでいく」私は素敵な最期の迎え方だなと思いました。親や家族が終末期に病院にいることを望めば、それを尊重したいと思いますが、私自身は、最期、家もしくは萬田先生のようなお考えの緩和ケア医がいる病院で迎えたいと考えています。
そして、自分が望む最期を迎えるには、主体的に生きることも必要なんだなと思いました。
講演の最後の質問コーナーで、萬田先生が「生きたようにしか死ねない」とお答えされていたのが印象に残りました。
私は、長谷川エレナ朋美さんが生き方のコーチで、萬田緑平先生が死に方のコーチだと思うのですが、「生きたようにしか死ねない」はこのお二人に共通するメッセージだな、と思いました。
死に方ついて考えることは生き方について考えること。
これからも考え続けていきたいテーマです。
関連書籍紹介
この講演会の関連書籍をご紹介します。
『家で死のう!―緩和ケア医による「死に方」の教科書』 萬田緑平 / 著
この講演会のきっかけともいえる本。今回のレポートで何か感じるものがあった方は、ぜひ、読んでみてください。
自分の人生が愛おしくてたまらなくなる100の質問ノート
「本当に大切なものを大切にする」には、まず自分を知ることが大切ですね。
ワークつきの書籍なので、実践しながら気づきを得ることができます。