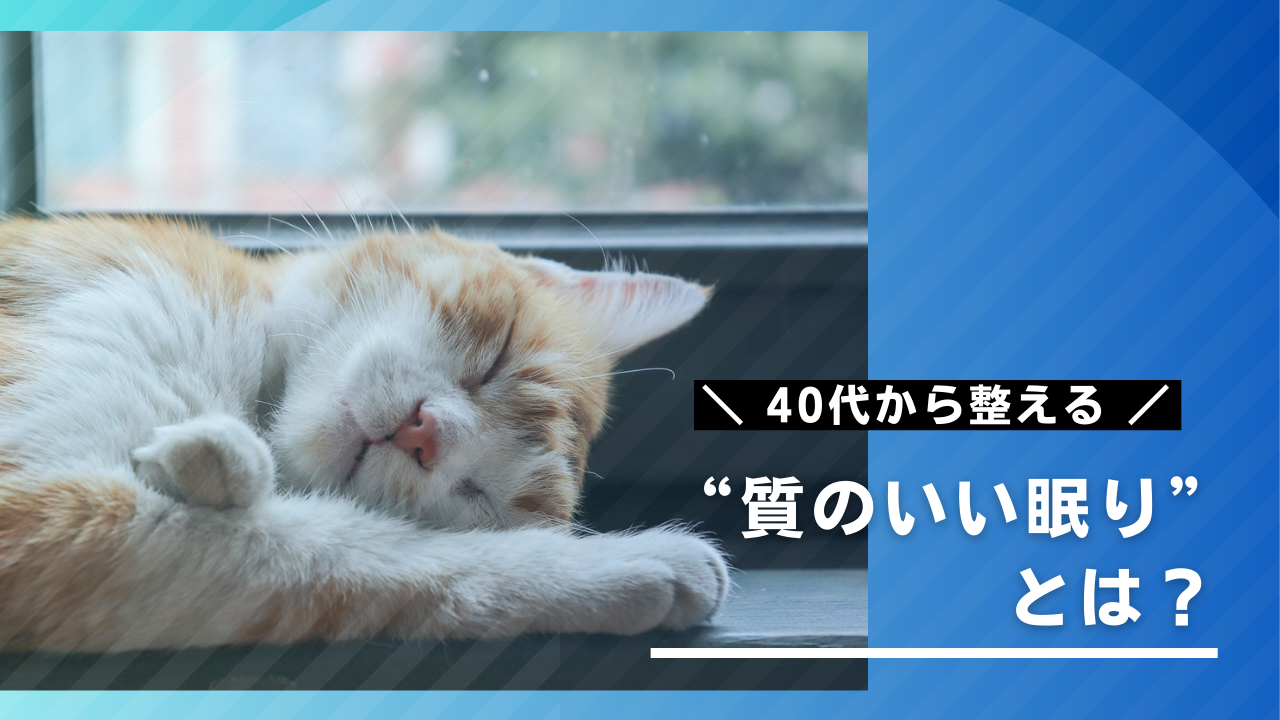「寝ても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」。
そんな睡眠のお悩みはありませんか?
40代は、仕事や育児、介護など多くの役割に追われながらも、自分の体調管理がより重要になる時期。睡眠でしっかり疲れを取り、エネルギッシュに活動したいものですよね。
今回は、「よい睡眠とは何か」など睡眠の質やお悩みをテーマに、本で学んだことや調べたことを共有します。
40代の睡眠の実態
40代は、睡眠時間や質に課題を抱える人が少なくないようです。まずは40代の睡眠の実態をみてみましょう。
6時間未満の睡眠が4割以上
厚生労働省による「国民健康・栄養調査」(※1)によると、
1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満の割合が最も高く、男性 35.2%、女性 33.9%である。6時間未満の者の割合は、男性 38.5%、女性 43.6%であり、性・年齢階級別にみると、男性の 30~50 歳代、女性の 40~60 歳代では4割を超えている。
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
とのこと。
睡眠時間6時間未満の人が4割を超えているとは!
その背景には、仕事・育児・介護など、複数の責任を抱えるライフステージならではの要因がありそうです。
実際に、身近な人の話を聞くと、子どものお迎えに間に合うように退社して、夕食にお風呂に大忙し。子どもが寝たあとは、残りの仕事を済ませてから就寝。翌朝はお弁当作りや夕食の下準備のために家族よりも早起き…。
となると、その睡眠時間にならざるを得ないのも想像ができます。
ホルモンバランス・生活リズムの変化
40代を迎える頃、女性の体内ではエストロゲンの減少などホルモンバランスに変化が起き始めます。その影響で、自律神経が乱れやすくなり、睡眠のリズムも乱れがちになるといいます。
産婦人科医の高尾美穂先生の著書(※2)でも、以下のような記述があります。
更年期を境に増えてくる不調の一つが「不眠」です。
『いちばん親切な更年期の教科書』著;高尾美穂
中でもとくに多いのが、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」です。
夜中に何度も目が覚めるのは、ホルモンバランスの影響もありそうですね。
加えて、仕事では管理職など責任のあるポジションに就く人も多くなり、子どもの進学や思春期、親の介護など家庭での役割も増加しやすい時期です。心身ともに多忙な日々が続く中で、いつの間にか「ぐっすり眠る力」が弱くなってしまっているかもしれません。
「よい睡眠」とは何かを知る
仕事に家庭にと忙しい日々だからこそ、40代からの睡眠は「量」だけでなく「質」が大切になります。よい睡眠とはどのようなものか、みてみましょう。
理想的な睡眠とは
まず、よい睡眠とは睡眠時間の長さではなく、「起きたときに心身がすっきりと整っているか」が基準となります。
個人差はありますが、一般的には、成人に必要な睡眠時間は7〜8時間とされています。
なかには短い睡眠時間でも耐えられる「ショートスリーパー」の方もいますが、それは遺伝によるものだそうです。2009年、米国カリフォルニア大学の研究チームが遺伝子の変異が短時間睡眠と関連していることを『Science』誌に発表(※3)しました。
今回、参考にした書籍『スタンフォード式最高の睡眠』(※4)の著者、西野精治氏もこの研究に関わっています。
そして、遺伝子がショートスリーパーにあたる人は人口のごく一部だそうです。
そのわりには「ショートスリーパー」を自称する人に出会う確率が高いなあと個人的に思います。
実は無理して短時間睡眠で過ごしていて、本人の自覚がないまま睡眠不足が慢性化しているなんてこともありそうな気がします。
入眠までの時間
ベッドに入ってからどれくらいで眠れているかも、睡眠の質を測るヒントになります。
「健常成人の平均睡眠潜時は10~20分」(※5)というデータもあるように、それくらいの範囲で入眠出来ていれば、寝つきに関しては問題ないようです。
一方、「おやすみ3秒」という言葉のようにすぐに眠れるのは、“眠り上手”のように思えますが、実は違います。これは睡眠不足が続いて脳が一気にスイッチを切っている“気絶に近い状態”である可能性もあるのだとか。
寝つきの良さ=良質な睡眠とは限らないのです。
私もかつては、「おやすみ3秒」の寝つきの良さを特技だと思っていましたが、慢性的な睡眠不足だったのだと思います。
深い眠り(ノンレム睡眠)とその重要性
私たちの眠りは、深い「ノンレム睡眠」と浅い「レム睡眠」が交互に現れます。この中でも、特に重要なのがノンレム睡眠。
深く眠っている間に、脳と体が本格的に休息し、次のような働きが促されます。
- 成長ホルモンの分泌(肌・筋肉の再生、免疫力の維持)
- 記憶や感情の整理・定着
- 細胞の修復・疲労回復
- 脳内の老廃物(アミロイドβなど)の排出促進
近年の研究では、深いノンレム睡眠中に、認知機能の低下に関与するアミロイドβのような老廃物を排出することが明らかになってきました。
つまり、ただ「長く寝る」だけではなく、「しっかり深く眠れるかどうか」が、心と体、そして脳の健康を保つ鍵となっているのです。
睡眠は最初の90分が重要
眠り始めて最初の90分は、最も深いノンレム睡眠の時間帯です。ここでしっかりと深く眠れるかどうかが、1日の睡眠全体の質を左右するといわれています。
ノンレム睡眠は一晩の間に何度か現れますが、その深さと持続時間は睡眠の後半に向かうにつれて徐々に浅く、短くなっていくことがわかっています。
つまり、最初の90分こそが、心身の回復に最も重要な時間帯なのです。
この90分間の質を高く保つには、「寝る前に体と心をゆるめる準備」をしておくことが大切です。
お風呂、照明、スマホからの距離、香りなど、睡眠前の環境を整えることで、自然な入眠と深い眠りを促すことができます。
睡眠のゴールデンタイムは夜10時から深夜2時ってホント?
かつては、夜10時から深夜2時は、成長ホルモンが多く分泌される「睡眠のゴールデンタイム」とよく言われていました。しかし最近では、睡眠の質は「何時に寝るか」よりも「どれだけ深く眠れるか」が重要という説が広まりつつあります。
つまり、ライフスタイルに無理してでも夜の10時~2時に睡眠を確保するよりも、最初の90分のノンレム睡眠をしっかり確保できる環境を整えることが大切なのです。
私自身のライフスタイルでは、10時に就寝するのが難しかったので、この説には励まされます。
理想の睡眠時間が確保できないときには
現代人は誰しも忙しく、7〜8時間の睡眠を毎日確保するのは簡単ではありません。そんなときは、「質を上げること」に意識を向けましょう。
『スタンフォード式最高の睡眠』では、このようなケースを例にあげています。
たとえば、すでに午前0時なのに、明日までに作らなければならない資料がある、というときは、
「眠気があるならまず寝てしまい、黄金の90分が終了した最初のレム睡眠のタイミングに起きて、資料にとりかかる」
ということをすすめています。
一方、眠気をこらえて明け方4時ごろに資料を作り終えて「せめて7時まで3時間寝よう」というのもよくある話だが、この場合、目が冴えてなかなか眠れない。」
とも。
確かにこれは我が身にも覚えあり、です。
眠気と戦いながら深夜や明け方まで作業しているうちに覚醒してしまって寝付けず、結局、徹夜したのと変わらない状態で出社、なんてこともありました。
40代からの睡眠改善ヒント
ここでは、忙しい毎日でもすぐに実践できる、睡眠の質を高める工夫を紹介していきます。
寝る前のNG習慣をやめる
「なかなか寝つけない」「途中で目が覚める」と感じる人の多くが、知らず知らずのうちに眠りを妨げる習慣を取り入れてしまっていることがあります。
代表的なのは、スマートフォンの使用。
スマホやタブレットから発せられるブルーライトは、脳を覚醒させる作用があり、眠気を遠ざけてしまいます。
寝室にスマホを持ち込まない、寝る1時間前からは画面を見ないなどの“デジタルデトックス”を意識するだけでも、睡眠の質は大きく変わるといいます。
実は私も寝る前のスマホ使用、ついついやってしまうのですよね。
スマホを目覚まし時計として使っているのもいけないのだと思います。アラームをセットした流れでつい、見てしまいます…。
スマホ以外の目覚ましに切り替えてみようと思っています!
どうしても、お酒を飲むなら…
「眠れないからお酒を飲む」という方もいますが、実はこれは寝つきをよくしているように見えて、睡眠の質を下げる習慣です。
アルコールは一時的に入眠を促すものの、睡眠の後半で中途覚醒が起きやすくなり、熟睡感が得にくくなってしまいます。
「わかってはいるけれど、やめられない」という方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、量とタイミングを意識することよさそうです。
『スタンフォード式 最高の睡眠』では、
「少量であれば寝つきも良くなるし、睡眠の質を下げない」
としています。日本酒換算で1~1.5合程度のアルコール量なら、寝る100分前までに飲むことで、寝つきが良くなり、翌日のパフォーマンスにも影響しにくいという報告があるそうです。
やめるのがストレスになるようなら、上手に付き合う工夫を取り入れるのがよさそうですね。
眠るための環境を整える
眠りの質を上げるには、「寝るための空間」を整えることも大切です。
照明は、就寝前に暖色系に切り替えることがおすすめ。間接照明やナイトランプなどで、明るさを抑えた環境にすることで、脳に「これから眠る時間だ」と自然に伝えることができます。
さらに、香りの力を借りるのもおすすめです。
リラックスを促す代表的な精油には、まずラベンダー。神経の鎮静や入眠促進をサポートします。
ほかに、ベルガモットも自律神経のバランスを整えるのにおすすめです。ラベンダーが苦手な方も柑橘系なら受け入れやすいのではないでしょうか。
精油はアロマディフューザーがなくても使えます。ティッシュに精油を1、2滴垂らして枕元に置くだけで充分ですよ!
カフェインの摂り方を見直す
眠りにくさの原因が、実は日中の過ごし方にあることも少なくありません。
特にカフェイン摂取のタイミングは、意識して見直したいポイントです。
書籍『SLEEP』(※6)によると、カフェインの摂取は午後2時までが理想とされています。
コーヒーなどに含まれるカフェインは、摂取後5〜8時間経たないと血中濃度が半分にならず、夜の眠りに影響を与える可能性があるからです。
ただし、1日3〜4杯程度などの適量の範囲内の摂取であれば、日中の集中力を保つなどのよい作用も期待できます。
私はコーヒーが好きで、1日に3~4杯程度飲みます。午後5時くらいまでは飲むこともありましたが、終了時間をもう少し早めてみようかなと思いました。
とはいえ、ディナーのあとにコーヒーを飲む場面など、たまにであればいいかな、と思っています。神経質になりすぎず、生活習慣を整えていければなあ、と。
心と体を整える“睡眠ルーティン”
眠りの質を高めるには、その前の過ごし方も大切です。心と体をゆるめ、自然と眠りに入っていけるような習慣を作りをご紹介します。
入浴で睡眠モードに
眠りに入るには、心と体が「休息モード」に切り替わることが必要です。
この切り替えを担っているのが、自律神経です。
日中は交感神経が優位になり、活動的になりますが、夜には副交感神経を優位にして、リラックス状態をつくる必要があります。
特に入浴は、就寝の90分前までに湯船につかることが理想的。
睡眠中は体の深部体温が下がる性質があります。入浴によって体の深部体温が一度上がり、その後自然に下がるタイミングで眠気が訪れやすくなります。そのタイミングを逃さずにベッドに入るのが大事ですね!
また、寝るまでに90分取れないときなどは、深部体温が上がりすぎないように、シャワーで済ませるのがベストなのだとか。
毎日続けたい「眠りのスイッチ習慣」
夜になったら「そろそろ眠る準備を始めよう」と体に知らせるための“合図”となる習慣があると、自然な入眠につながります。
たとえば、
- 照明を落とす
- パジャマに着替える
- ハーブティーを飲む
- 精油を焚く
- 簡単なストレッチやマッサージをする
こうした“眠りの儀式”を決めておくことで、心と体が「寝るモード」へと自然に切り替わりやすくなります。
就寝リズムを一定に
就寝時間と起床時間を一定にすることが大事というのはよく聞く話です。
『スタンフォード式 最高の睡眠』でさらに興味深いことが書かれていました。
それは、
通常就寝する時間の直前から2時間前あたりがもっとも眠りにくい」
「後ろにずらすのは簡単、前にずらすのは困難」これが睡眠の性格なのだ
ということ。
なので、明日はいつもより早く起きる必要があるときにも、1時間早く寝るのではなく、いつも通りの時間に寝て、睡眠時間を1時間削る方が睡眠の質を高く保ちやすい、のだそう。
これ、私も思い当たるところがあります。
出張で早起きだからと早く寝ても、結局寝付けず、それが焦りとなっていつもの時間になっても寝付けないなんてことがありました。
それでも「早く寝ていつもと同じ睡眠時間を確保したい!」という場合には、早く寝たい分だけ早くお風呂に入るのがよいそうです。
眠れないときの対処方法
ベッドに入ったのに眠れない。そんな夜は誰にでもあるものですよね。
ここでは、眠れないときの対処方法をご紹介します。
○分以上寝つけなかったら起き上がる
ベッドに入ったまま「眠れない」「寝不足で明日が心配」などと考えていると、脳は“ベッド=眠れない場所”として認識してしまいます。
これは不眠の悪循環に陥る原因となるため、20〜30分経っても眠れないときは、一度起き上がることが推奨されています。
別の部屋で静かに本を読んだり、アロマを焚いてゆったりと過ごすなど、“眠りのプレッシャー”から自分を解放することが大切です。
再び眠気が来るのを待つ
眠れない夜には、「眠らなきゃ」と思うほど眠れなくなるものです。そんなときこそ、焦らないことが大事です。
スマートフォンやテレビなどの強い光は避けて、できるだけ自然なリズムの中で再び眠気が戻ってくるのを待ちましょう。
ぬるめの白湯を飲んだり、深呼吸をするだけでも、心が落ち着いてきます。お気に入りの本を開いたり、小さな音でヒーリング音楽をかけてもよいかもしれません。
まとめ
40代の睡眠は、「睡眠の質」に注目することが大切だとわかりました。
ホルモンバランスの変化、生活の忙しさなど、睡眠の質が揺らぎやすい時期だからこそ、自分にとって心地よい眠り方を見つけていきたいですね。
まずは、寝る前の習慣や環境を見直し、“最初の90分の深い眠り”をしっかり守ることから始めてみましょう。
【参考・出典】
※1:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf
※2:『いちばん親切な更年期の教科書』著:高尾美穂
※3:He, Y. et al., Science, 2009.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1174443
※4:『スタンフォード式 最高の睡眠』著:西野精治
※5 : J-STAGE|睡眠潜時の平均に関する統計
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamt/66/J-STAGE-2/66_17J2-13/_html/
※6 『SLEEP 最高の脳と身体をつくる睡眠の技術』著:ショーン・スティーブンソン